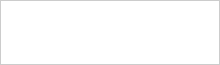先日行った、2回目の患者満足度に対するスタッフとの話し合いで、課題にでたフィジカルアセスメントをさっそく所内研修で企画しました。
なかなか、平日みんなが落ち着いて学習することができないので、忘年会の前に3時間早めに来て、休日の静かなステーションで、研修会を行いました。
本部の認定看護教育課程の教員でもあり、あすか山STで、一緒に働いていた松井さんにもスペシャルゲストで、一緒に講義をしていただきました。
まず、事例提議し、各自のフィジカルアセスメントをしてもらい、それを出し合い、何を優先に見て、判断するか、そのエビデンスはなにかを確認しました。
そのあと、松井さんから、救急の視点での講義、その後、人型の紙に体の臓器をはりつけながら、心臓や、肝臓のスクラッチのしかた、心臓、肺の実際の音のCDを聞きました。
その人型の紙を囲んで、みんなの経験を出し合い、フィジカルアセスメントの知識、技術などの共有を図りました。
医師への報告をどのような内容にすべきか、フィジカルとった項目の「異常なし」を伝えることも大切と話し合いました。
第1弾の企画としては、よかったかなと思います。
第2弾以降は、より詳細なフィジカルアセスメントと、それにつなげる看護ケアなど企画していきたいと思っています。
この直後の忘年会は、大変盛り上がり、大笑いで楽しかったです。
学び、遊びのバランスが大切だと思います。
忘年会の席で、今年あすか山に来てくれたスタッフに「学習会での平原さんと今の平原さんの差に驚きます」と言われ、どちらも私よ、と笑ったものの、「腹踊りや、安来節のできる自分をだすのは、もう少し先に延ばさなくては、」とひそかに思いました。