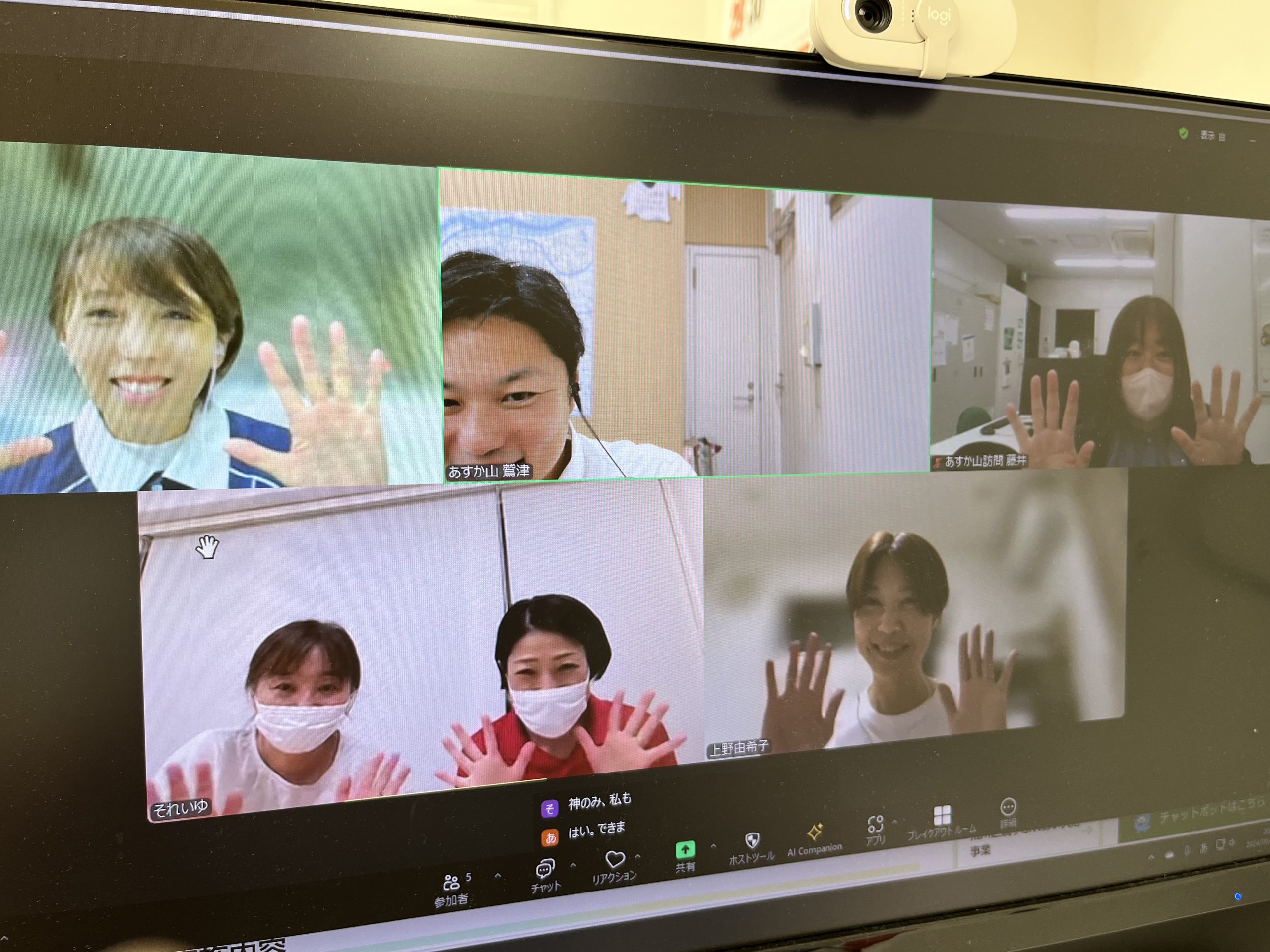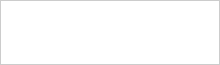先日、私たちのステーションの在宅看護専門看護師が
北区小児訪問看護を支える会(通称SUKU♡SUKUすくすく)に参加してきました。
(※地域の訪問看護ステーション協議会の活動の一環です。)
令和6年度第2回のSUKU♡SUKUは
「外国籍の家族への小児訪問看護としての関わりについて、皆で情報交換しよう!!」
というテーマで、
区内の訪問看護ステーションのベテラン所長さんから事例提供を頂きました。
事例の対象者は外国にルーツがある医療的ケア児である双胎児であり、
両親や祖父母それぞれの日本語のコミュニケーション能力も違うという世帯でした。
活発に意見交換をしながら、
小児訪問看護について学ぶことができました。
患者と看護師に、言語やコミュニケーション、
文化の違いがある中、
医療的なこと、各種制度等の家族の共通理解を得ていくことは
とても難しさがあることを共有しました。
今回の事例提供をいただいたそのステーションには、
なんとその子の母国語を話せるスタッフがいるという状況があったことも共有され
参加メンバー一同で驚いたり、羨んだりしました。
(珍しいですよね。)
日本に住む、私たちの価値観や、文化、看護観を
当たり前のように、相手に押し付けることなく
丁寧に、丁寧にアプローチしていくことで、
訪問看護を受ける本人や家族も、
とても心強く安心するのだろうと考えました。。
今回も参加者のメンバーの様々な小児看護経験なども共有することができました。
(以下に列挙します)
「障害受容」についての一般的なモデルの、どの段階にいるかも、
その国の文化やその国の社会でどのように「障害」が捉えられているかによって
把握しにくい・・・、
同じ国の医ケア児や障害児をもつ先輩ママを見つけだすことができれば、
結果的に看護がスムーズにいくこともあること・・・、
母の負担軽減のために障害福祉以外の
自治体の育児支援制度やボランティアの活用するようなアイデアもあること
双子の訪問の訪問看護についての、ステーションとしてケアの入り方(算定方法)など
国土の広い国の場合や、多民族が同居するような国の場合は、
同じ国だからといって同じだと思わないことが必要、
離乳食はお国の風習(ヒツジ肉、ヤギの乳等)がある、
などなど多くの看護実践の中での知見を、小児訪問看護の臨床家として語らい合いました。
次回は 12月4日(水)18:30~(zoom開催)。
この会にご興味のある方はぜひ「北区訪問看護ステーション協議会」
までお問い合わせください。
職種や経験の有無は問いません。
訪問看護の仲間に門戸は開いております。
次回も楽しみです!!